- AIアプリ スノーって重要なの?
- AIアプリ スノーってどうやって使うの?
- AIアプリ スノーでの作曲をしたい!
こんな悩みを解決できる記事になっています!
書き出し
なぜなら、これからご紹介する
『AIアプリ スノーの使い方』
を実施したことで、
当ブログでは一人当たりのユーザー数に対する
PV数が2倍に上昇したからです。
記事の前半では
『AIアプリ スノーの定義』
などを解説しつつ、
記事の後半では
『AIアプリ スノーの使い方』
を具体的に解決します。
この記事を読み終えることで、
『AIアプリ スノーの使い方』
が理解できるだけではなく、
ワークを通して
『AIアプリ スノーの使い方』
が身についた状態になります。
↓ご覧のスポンサーの提供でお送りします。
目次
【AI】Sunoアプリをプロンプトなど使って楽曲生成を楽しむ件!

Sunoアプリは、
プロンプトで歌詞スタイルやジャンルを指定するだけで、
AI作曲が楽しめる革新的ツール。
初心者でも簡単に本格的な楽曲を生成でき、
細かいカスタマイズも可能。
無料プランでも十分楽しめ、
音楽制作の民主化を実現している点が魅力的。
Sunoアプリが人気な理由は、
音楽知識不要で誰でもプロの楽曲を作れる手軽さにある。
テキストプロンプトだけで作曲・編曲・歌唱まで自動生成され、
創作の敷居を劇的に下げた。
また、生成速度が速く、多様なジャンルに対応し、
商用利用も可能な点が支持されている。
メモ
私は、オルタナティブ・ロックの
女性ボーカルのファイル音源が欲しかったため、
楽曲制作の後でボーカルなどが
出力されるのでそちらを使いたいと思いました。
使い方も人それぞれだと感じました。
私には音楽のバンドの可能性を思い出させてくれましたが
現段階でV5ですが、V4.5のバージョンが個人的には良かったかなと思っています。
Sunoは音楽制作を完全に民主化し、
プロンプト入力だけで誰もがアーティストになれる時代を実現。
技術的障壁を取り除き、
アイデアさえあれば即座に楽曲化できる革命的ツール。
今後は人間の創造性とAIの技術力が融合し、
新たな音楽文化が生まれる可能性を秘めている。
↓ご覧のスポンサーの提供でお送りします。
Sunoでボーカルの波形wavファイルが欲しい

Sunoで生成した楽曲からボーカル波形を抽出するには、
ダウンロードした音源を外部のステムセパレーターツール
(UVR5、Demucs、LALAL.AI等)で処理する必要はない。
Suno自体にはボーカル単独の書き出し機能はあるので、
別途音源分離作業が必須はないです。
ボーカル波形が欲しい理由は、リミックス制作、
カラオケ音源作成、他DAWでの編集、
ボーカルエフェクト追加などの二次創作ニーズがあるため。
また、歌声だけを別プロジェクトで使用したり、
音程修正、ハーモニー追加など細かい加工を行うためにも
単独ファイルが必要となる。
メモ
上記と繰り返しになりますが、
私がV4.0を使っている時V4.5から
Stems(波形摘出機能)が追加され、
分離ツールのAIツール課金をやめました。
そして新しいバージョンが全部いいのかは
分からないという事ですね。
これも癖のある表現かもしれませんが、
現実そうですね。上手いプロンプト(指示だし)がカギかもしれませんね。
Sunoのボーカル抽出はV4.5から可能だが、
需要の高さから将来的にステム分離機能の実装済みです。
UVR5等の無料ツールで対応可能でもありますが、
AI音源分離技術の進化により品質も向上中。
クリエイターの柔軟な音楽制作(ハモリ、コーラス分離)には
不可欠な機能となっている。
↓ご覧のスポンサーの提供でお送りします。
Suno AIで曲を生成する方法

Suno AIの曲生成は驚くほどシンプル。
プロンプト欄に
「ポップな恋愛ソング」等と入力するか、
Custom Modeで歌詞とスタイルを個別指定して
生成ボタンを押すだけ。
AIが作曲・編曲・ボーカルまで全自動で処理し、
プロ級の楽曲が数十秒で完成する画期的システム。
Suno AIが簡単に曲を生成できる理由は、
最先端の深層学習モデルが膨大な楽曲データを学習し、
テキストから音楽要素を自動解析・構築するため。
複雑な音楽理論や制作技術をAIが代行し、
ユーザーはアイデアを言語化するだけで、
プロレベルの編曲とボーカル生成が実現する。
メモ
私はMIdi鍵盤で打ち込みでメロを作り、
オーディオファイルでメロディーwavファイルを作る。
そこで大体決まる。
プロンプトも曲の速さと女性ボーカルの指定等を入力、
これだけで十分な音楽を抽出してくれる。
あとはStemsからボーカルファイルを摘出、
ハモリもついてきます、
ハモリを外すにはAIオーディオ摘出ファイル
サービスを使う必要があります。
Suno AIは「アイデアを音楽に変換する翻訳機」として機能し、
言葉を入力するだけで完成曲が生まれる革新性が本質。
従来の作曲に必要だった技術・時間・費用の壁を完全に撤廃し、
創造性さえあれば誰もが音楽表現できる
新時代のクリエイティブツールとして確立している。
↓ご覧のスポンサーの提供でお送りします。
最初のステップは依頼文を書くこと
最初のステップである依頼文作成は、
成果物の品質を決定する最重要工程。
明確な要件定義、具体的な指示、
期待する成果の記述により、
認識のズレを防ぎ効率的な進行が可能になる。
曖昧な依頼は修正の繰り返しを生むため、
初期段階での丁寧な文書化が成功の鍵となる。
依頼文を最初に書く理由は、
頭の中の漠然としたイメージを言語化することで要件が明確化し、
実現可能性の検証ができるため。
また、文書化により関係者間で共通認識が生まれ、
後工程での手戻りを防げる。
思考の整理と情報共有を同時に実現し、
プロジェクトの土台を固める効果がある。
メモ
紙などを使って大まかなメモやアイディアを書いて
使えそうなもので少しづつ形にしていく。
焦る必要はない、時間を作る必要性は
あるかもしれないですね。
なんでもそうですが空いている
時間を作るのも実力のうちですよ。
その日の調子や運なども含めてそれも
実力思考ではないかと思いました。
依頼文作成は単なる手続きではなく、
プロジェクトの設計図を描く創造的行為。
ゴールを言語化する過程で思考が整理され、
実行可能な計画へと昇華される。
優れた依頼文は相手の行動を導く羅針盤となり、
双方の時間と労力を最適化する投資対効果の高い初期作業である。
できあがった曲に手を加えていきましょう
生成された曲への手直しは、
AI作品を自分だけの作品に昇華させる重要プロセス。
音量調整、エフェクト追加、
パート差し替え、テンポ変更など細かな編集により、
汎用的なAI楽曲が個性的な作品へ変貌する。
完成度を高めつつオリジナリティを注入する
創造的な仕上げ作業となる。
手を加える理由は、
AI生成曲は技術的に優れていても画一的になりがちで、
個人の感性や意図を完全には反映できないため。
細部の調整により楽曲に魂を吹き込み、
聴き手に響く独自性を付加できる。
また、編集過程で音楽制作スキルも身につき、
AIと人間の共創による新たな表現が生まれる。
メモ
これはありますね、
ここのメロディーちょっと原曲のうまみだとかありますね。
自分で歌ってもいいが、
歌唱力もプロンプト同様で上手くしないと
抑揚などが弱ってきたり自分の声をのせる時に
AI(アカペラ)と何かの役に立つ。
元にボイトレは無駄ではないのだなと思ってきている。
AI楽曲の編集は「共同作曲」の最終章であり、
機械の効率性と人間の感性が融合する瞬間。
手を加えることで単なるAI生成物から「自分の作品」へと昇格し、
クリエイターとしての達成感も得られる。
この人機協働こそが、
次世代音楽制作の理想的な形として定着していく。
「歌詞テキスト」(作詞)
歌詞テキストの作詞は
楽曲の魂を決定づける核心要素。
言葉選び、韻律、メロディとの調和により
聴き手の感情に直接訴えかける力を持つ。
AI時代でも人間の体験や感情から生まれる
歌詞には独自の説得力があり、
普遍的なメッセージと個人的な表現の
バランスが名曲を生む鍵となる。
作詞が重要な理由は、
歌詞が楽曲の感情的な核となり、
聴き手との共感の架け橋となるため。
メロディーだけでは伝えきれない具体的なストーリーや思いを言語化し、
記憶に残る印象を作る。
また、歌詞の響きやリズムが曲全体のグルーヴを左右し、
歌い手の表現力を引き出す土台にもなる。
メモ
私は自分で書いた歌詞をボイトレをして歌って、
それからSunoに入力して(Wavファイル)として、
バージョンも古い方がうまくいくときがあります。
なぜかは分かりませんが、
ちょっとした抑揚がなんともいい時もあるはずだからです。
まだ触ってないこともあるからです。
作詞は時代を超えて人の心に残る「言葉の建築」である。
優れた歌詞は単なる文字の羅列ではなく、
メロディと融合して新たな感情体験を創造する芸術作品。
AI時代においても、
人生の機微を捉えた言葉選びと普遍的な共感を呼ぶ表現力は、
人間にしか紡げない創作の最後の砦となっている。
ジャンルなどの設定
ジャンル設定は楽曲の方向性を決定する羅針盤であり、
リスナーの期待値を形成する重要な要素。
ポップ、ロック、ジャズなど
各ジャンルの特徴を理解し適切に選択することで、
ターゲット層に響く作品が生まれる。
複数ジャンルの融合により独自性も演出でき、
音楽的アイデンティティを確立する基盤となる。
ジャンル設定が必要な理由は、
音楽制作の枠組みを明確にし、
使用する楽器、リズムパターン、
コード進行などの選択基準を提供するため。
また、配信プラットフォームでの分類や、
リスナーの検索・発見を容易にする。
制作の効率化と市場での位置づけを
同時に実現する戦略的な決定事項である。
メモ
私も個人的にコード進行の書籍を買って学習しています。
それをDawアプリを使って短い動画(YouTubeショート)
にして様子をうかがっています。
アドリブだけど短いフレーズを使って、
それをどうやって繋げればいいかなど思考を積んでいます。
多分私は遅咲きな方だと思うので
YouTubeのアナリティクスを見ているとどこまで
聞かれたとか聞かれないとか分かります。
少しでもバズったりする動画は
絶妙なタイミングなんですよね。
ジャンル設定は創造性の制約ではなく、
無限の可能性を整理する創作の出発点。
既存の型を理解した上で、
境界を越えた実験や融合により革新が生まれる。
適切な設定は制作の指針となり、
聴き手との共通言語を作りつつ、
その期待を良い意味で裏切る余地も残す、
音楽表現の戦略的フレームワークである。
想定視聴者の指定
想定視聴者の指定は楽曲制作の精度を飛躍的に高める戦略的決定。
年齢層、ライフスタイル、音楽嗜好を明確化することで、
歌詞の言葉選び、サウンドの質感、テンポ設定まで最適化される。
ターゲットを絞ることで深い共感を生み、
結果的により強いファンベースを構築できる制作の要となる。
想定視聴者を指定する理由は、
万人受けを狙った楽曲は誰の心にも深く刺さらないため。
特定層の価値観、悩み、憧れを理解し反映させることで、
強い感情的つながりが生まれる。
また、プロモーション戦略も明確になり、
SNSでの拡散や配信アルゴリズムでの
表示最適化にも直結する実践的な施策である。
メモ
今これを書いている時点では
YouTubeでウケないものはどこでもダメなんじゃないかなと思う。
自分の視点で書いているので気まぐれだし、
またそれがいい味を出しているといいなと思います。
決めつけではないが、
評価はしてもらった方が自分でもありがたいと思います。
想定視聴者の指定は
「誰かのための音楽」を作る愛のある選択。
全員を喜ばせようとして誰も感動させられない罠を避け、
特定の人々の人生に寄り添う作品を生む。
この的確なターゲティングこそが、
音楽を単なる音の羅列から、
聴き手の記憶と感情に刻まれる特別な体験へと
昇華させる秘訣である。
ファイル名の指定
ファイル名の適切な指定は、
楽曲管理の効率性と将来の検索性を左右する基本作業。
日付、バージョン、ジャンル、テンポなどを体系的に命名規則化することで、
大量の楽曲でも瞬時に特定可能。
共同作業時の混乱を防ぎ、バックアップや配信時のミスも削減する、
プロフェッショナルな制作環境の第一歩となる。
ファイル名指定が重要な理由は、
制作が進むにつれ類似ファイルが増殖し、
「最終版_本当に最終.wav」のような混乱を招くため。
統一された命名規則により、バージョン管理、
コラボレーターとの共有、将来の再利用が円滑になる。
また、配信プラットフォームへのアップロード時の
メタデータ管理にも直結する実務的必須事項。
メモ
私は西暦と日付、曜日、曲のタイトルを打って、
フォルダも作って管理しています。
早いうちにやっていると、すぐに調べられて便利です。
これもずっと前から考えていたため有利に働きます。
まずは遊びから始めたり、実験的でもいいと思います。
自分がわかりやすく、誰でも分かりやすいものがいいかなと個人的に思います。
ファイル名は楽曲の「デジタル身分証」として機能し、
創作の歴史を記録する重要な情報資産。
適切な命名は単なる整理術を超えて、
制作プロセスの可視化とナレッジの蓄積を実現する。
未来の自分や協力者への贈り物となる、
一見地味だが創作活動を支える確かな基盤構築作業である。
Suno AIのサービスプラン

Suno AIは無料プランで月50曲、
有料プランは月$10で500曲、
$30で2000曲生成可能な柔軟な料金体系。
趣味利用なら無料版で十分、
本格的な制作には有料版が適している。
商用利用権も有料プランに含まれ、
コストパフォーマンスは従来の
音楽制作と比較して圧倒的に優れている。
このプラン設計の理由は、
幅広いユーザー層のニーズに対応するため。
無料プランで参入障壁を下げて新規ユーザーを獲得し、
使用量に応じた段階的な料金設定で収益化を実現。
商用利用権を有料プランに限定することで、
ビジネスユーザーからの適切な対価回収と、
趣味ユーザーの気軽な利用を両立させている。
メモ
円安のせいで日本円でクレジットカード払いだと高くはなる。
ここが使えるかどうかでかなり環境が変わってくる。
まだ私はAIに3つとサブスクで3つ以上はらっている。
それでもなんとかできている。
今の環境をフルに活用して対応していければと
思ってす1年以上経ちますかね。
Suno AIのプラン設計は音楽制作の
民主化を体現する絶妙な価格戦略。
無料で始められる敷居の低さと、
プロユースにも対応する拡張性を両立。
月額$10から商用利用可能という破格の設定は、
従来の音楽制作コストを革命的に変え、
クリエイターエコノミーの新たな可能性を切り開いている。
↓ご覧のスポンサーの提供でお送りします。
本格的に使うなら有料プランを選ぼう
本格的な音楽制作には有料プランが必須。
月500曲以上の生成枠、商用利用権、
優先処理、高音質出力など、
プロフェッショナルな活動に不可欠な機能が揃う。
月額$10という投資で無限の創作可能性と収益化の道が開け、
従来の音楽制作コストと比較すれば破格の費用対効果を実現できる。
有料プランが必要な理由は、
無料版の月50曲では試行錯誤や
複数プロジェクトの並行作業に限界があるため。
商用利用権がないと収益化できず、
生成待ち時間も長い。
プロ活動では大量の試作と迅速な納品が求められ、
クライアントワークや配信収入を考慮すれば
月額料金は即座に回収可能な必要投資となる。
メモ
有料プランでないとボーカルの波形の
Wavファイルをダウンロードできないので、
私は全てはここにつながっている。
これからどうなるのか考えることにもはやちゅうちょもない。
とにかくコードを書いてメロを作成しなければならない。
これも毎日コツコツとやるしかない。
環境の奴隷になることが大事である。
有料プランは「趣味から仕事へ」の
転換点を象徴する賢明な投資判断。
無制限に近い創作自由度と商用利用権により、
アイデアを即座に収益へ変換できる。
月額わずか$10で得られる
生産性向上と機会創出を考えれば、
音楽クリエイターにとって最もROIの高い
自己投資となる必然的な選択である。
無料・有料プランの相違点
無料プランは月50曲で非商用のみ、
有料は月500曲以上で商用利用可能という決定的な差がある。
さらに有料版は優先キュー、同時生成数増加、
ダウンロード無制限など作業効率が大幅向上。
趣味なら無料で十分だが、
収益化や大量制作を目指すなら有料プランへの移行は
避けられない分岐点となる。
プラン差別化の理由は、
ビジネスモデルの持続可能性と
ユーザー価値の最大化を両立させるため。
無料版で製品価値を体験させつつ、
本格利用者には対価に見合う付加価値を提供。
商用利用権の有無で収益機会を分け、
処理優先度の差により、
サーバーリソースを効率的に配分する
戦略的な設計となっている。
メモ
Dawでボーカルの波形が必要な場合は課金しなければならない、
それでも課金する必要性は自分自身にかかっている。
すぐに動きたい場合は即課金ですね。
私は即課金しました、
とりあえず安定したボーカルが必要だったからです。
本格的にやるにはなるべく早く課金して、
上手いボーカルはどこが自分と違うのかを聞けますし
見れますので将来をみすえて課金しましょう。
無料と有料の境界線は
「趣味と仕事」「消費と生産」を分ける明確な線引き。
無料版は音楽制作の楽しさを知る入口として機能し、
有料版はその楽しさを価値に変換する出口となる。
この段階的な設計により、ユーザーの成長に寄り添いながら、
クリエイターエコシステム全体の発展を促進する巧妙な仕組みである。
初心者ほどピュアに学べる
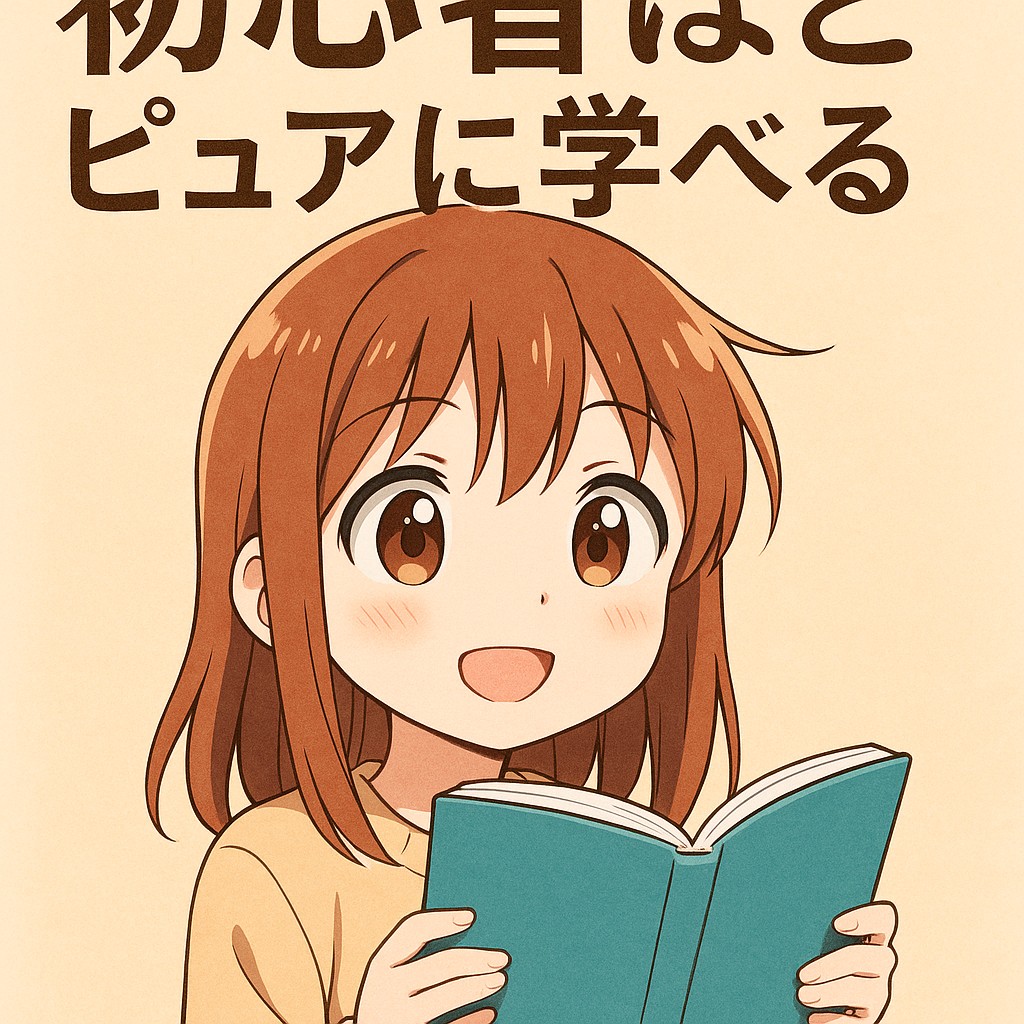
初心者は先入観や固定概念がないため、
新しい技術や手法を素直に吸収でき、
革新的なアプローチを恐れずに試せる強みがある。
経験者が陥りがちな「こうあるべき」という制約から自由で、
失敗を恐れず実験的な挑戦ができる。
この純粋な好奇心と柔軟性こそが、
既成概念を超えた創造的なブレイクスルーを生む原動力となる。
初心者がピュアに学べる理由は、
過去の失敗体験や成功体験に縛られず、
全てを新鮮な視点で捉えられるため。
専門知識がないことで逆に本質的な問いを投げかけ、
常識を疑える。
また、できない前提で始めるため小さな成功にも喜びを感じ、
学習モチベーションが高く維持される。
白紙の状態が最大の可能性となる。
メモ
知らないことは検索すれば出てくるけど、
結局は人間なので人の助けが必要になってくる。
何かが見え隠れしているようになれば
必要に応じて判断する能力を
磨くことで前へ進めることができる。
サービスとはいえお互い人間のである
感覚を再感覚する必要がある。
音楽もその人のココロが
現れるもの力して臨むことですね。
初心者の「知らない強さ」は、
イノベーションの源泉となる貴重な資産。
専門家が見落とす素朴な疑問から画期的な発見が生まれ、
型にはまらない自由な発想が新境地を開く。
ビギナーズマインドを保持することは、
どんな分野でも成長し続けるための必須条件であり、
経験を積んでも忘れてはならない原点である。
↓ご覧のスポンサーの提供でお送りします。
Sunoのボーカルと掛け合いができる

Sunoのボーカルとの掛け合いは、
AI歌声を活用した新たな音楽表現の可能性を開く。
生成されたボーカルトラックに人間の歌声を重ねたり、
コール&レスポンス形式でデュエットを構築可能。
バーチャルシンガーとのコラボレーションという未来的な制作スタイルが、
一人でも豊かなハーモニーを生み出せる環境を実現している。
掛け合いが可能な理由は、
Sunoが生成する歌声が音程・リズムが正確で、
人間の歌声と調和しやすい品質を持つため。
また、ステム分離技術により伴奏と
ボーカルを個別に扱え、DAWでの編集が容易。
一人では表現できないハーモニーやデュエットを
仮想パートナーと実現でき、
制作の孤独感も解消される創作の新形態。
メモ
私はエレキギターを弾くので
ボーカルのメロディーに
掛け合わしたりしながら演奏を楽しんでいます。
時と場合にもよりますが
楽しいギターライフの幕開けでありますね。
Sunoはボーカルのマスタリングされた音源ですので、
たまにエラー的なことが起きますが先日、
V5のバージョンアップにより
更なる発展があったとのことで楽しみですね。
Sunoとの掛け合いは「一人バンド」から
「AIとのバンド」への進化を象徴する画期的な共創スタイル。
孤独な宅録アーティストに理想的な歌唱パートナーを提供し、
創造力の限界を解放する。
この人機融合の音楽制作は、
新たな表現領域を開拓し、
未来の音楽シーンにおける標準的な制作手法として
定着していく可能性を秘めている。
↓ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。